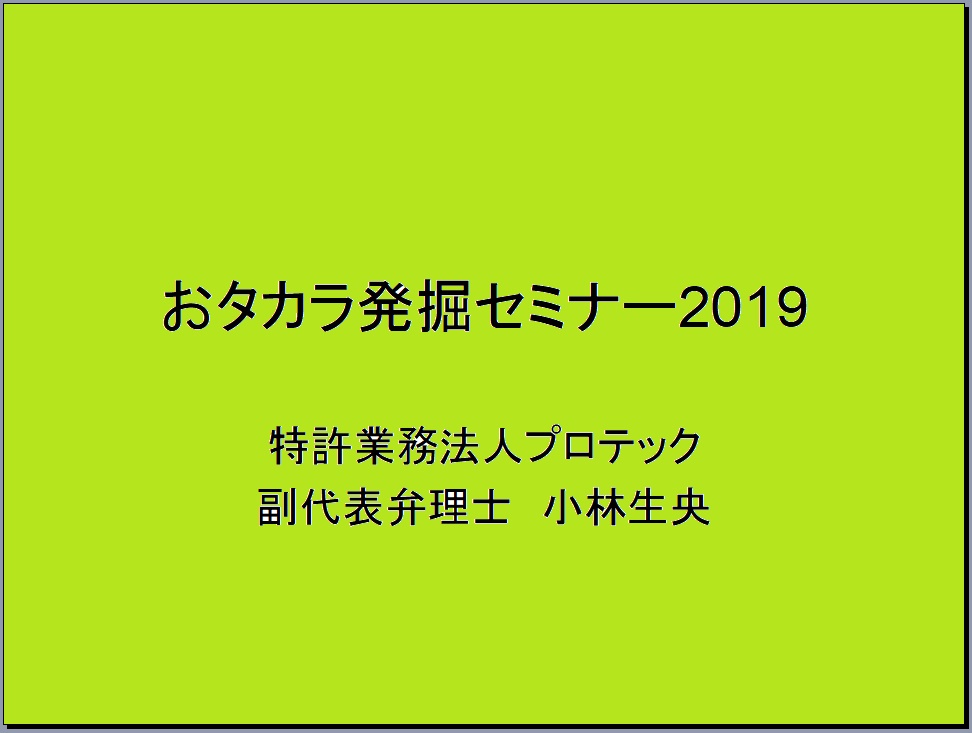
2019年2月13日水曜日18時から弊所会議室にて
おタカラ発掘セミナーを開催しました。
講師一名と
お客様お二人、
合計3人で二時間近く、
活発な議論が交わされました。
コンピュータの絡む特許、
コンピュータの絡まないシステム特許(いきなりステーキ)、
を中心に特許のねらい目がどこにあるか
浮き彫りにすることができたと
感じています。
3月も行いたいと考えています。
近々、お知らせするつもりです。
ご期待ください。
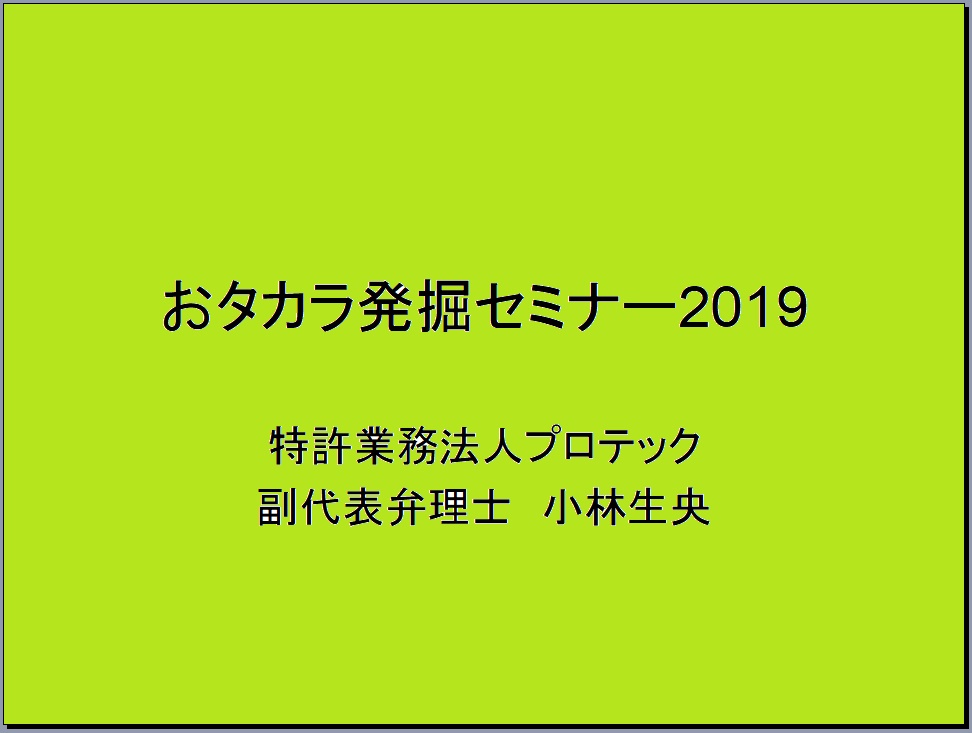
2019年2月13日水曜日18時から弊所会議室にて
おタカラ発掘セミナーを開催しました。
講師一名と
お客様お二人、
合計3人で二時間近く、
活発な議論が交わされました。
コンピュータの絡む特許、
コンピュータの絡まないシステム特許(いきなりステーキ)、
を中心に特許のねらい目がどこにあるか
浮き彫りにすることができたと
感じています。
3月も行いたいと考えています。
近々、お知らせするつもりです。
ご期待ください。
自己資本だけで、
商標登録、特許などを進めるのはたいへんです。
ふるさと名物応援事業の補助金を受けることをお勧めします。
平成29年度の例を見ると、2月に公募。3月締め切りのようです。
平成30年度の公募に注目することをお勧めします。
弁理士ブログランキングにエントリーしています。
このバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
順位があがります。
大学ジャーナルによると、
国立大学研究者による発明では、
特許出願の査定率
(出願審査請求されたもののうち、特許取得される割合)が
2000年ごろは、56パーセントほどだったのに対し、
2010年を越えてからは、80パーセントほどに上がっているとのこと。
一般的な査定率は、65パーセント。
ちなみに、
我が、特許業務法人プロテックの特許査定率は、
80パーセント強です。
弁理士ブログランキングにエントリーしています。
このバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
順位があがります。
わが国特許庁が最近発表したところによると、
ビジネス関連発明の特許査定率(権利取得率)が上昇しています。
2000年ごろには、10パーセントだったのが、最近は70パーセントまで上がってきています。
IoT(インターネットオブシングズ)の傾向になってきたのが、一つの要因であろうと考えます。
コンピュータと、物とのからみで新しいビジネスがどんどん生まれていると考えられます。
以前、拒絶が多かった頃には、コンピュータ抜きでもできるビジネスをコンピュータで表現しただけのものが拒絶されていたという傾向がありました。
IoT ビッグデータ 人工知能
新しい時代のキーワードが見えてきています。
https://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm
特許庁の記事をよむにはこちらをクリックしてください。
政府がすすめる地方創世の波にのり、全国各地で地域のあらたな名産品開発が活発化している。地域産品といえば、「地域ブランディング」や「地域団体商標」といった言葉が先行して聞こえてくるが、農林水産物のブランドでは、実際には、農林水産省が担当する「地理的表示保護制度」や種苗の「育成者権」と、特許庁が担当する商標・意匠・特許の双方が関係し、地域ブランドの推進にはそれぞれの知的財産保護や戦略が必要になってくる。
そんななか、特許庁と農林水産省が協力し、平成28年10月から、各都道府県に設置している知的財産総合支援窓口[=(独)工業所有権情報・研修館が所管]に於いて、地理的表示保護制度や種苗の育成者権についても相談受付をスタート。制度や所轄省庁の壁を超えた知的財産サービスが始まっている。
また最近の傾向として挙げられるのが、特許の取得だ。田辺市とJA紀南は、インフルエンザウイルスを抑制する梅酢ポリフェノールを共同出願。和歌山大学食農総合研究所の協力で実現したもので、いったん拒絶査定になったものの、不服審判で審判官面接して登録に持ち込んだそうだ(特許第6049533号)。請求項1では 「 梅酢ポリフェノールを有効成分として含み、クエン酸を含まない抗ウイルス剤」 と非常にシンプルで広い権利範囲。 地域の名産品で健康増進効果もありとなれば、商品価値は非常に高くなりそうだ。
食品の用途特許に注目
こうした健康食品の特許取得の背景になっているのが、2016年4月に運用が開始された食品の用途特許に関する審査基準の改定(緩和)だ。生鮮食品を除く機能性表示食品やトクホなどの加工食品が対象で、従来、用途限定の記載として認められなかったものが認められるようになった。 例えば「成分Aを有効成分とする二日酔い防止用茶飲料」 「成分Bを有効成分とする歯周病予防用グレープフルーツジュース」 など、有効成分の発見に新規性があれば特許となるのだ。
さらに──田辺市・JA紀南では、和歌山信愛女子短期大学に研究協力をあおぎ、介護食用に“種も皮もない梅干し” を開発し製法特許を出願中。食事意欲を増進させ、唾液量がふえることで口腔内を清潔に保つことにつながるのだそうだ。
JA紀南ではこのほかにも近畿大学や明石酒造(株)、宮崎県などとそれぞれに食品の特許を共同出願している。共同出願というタッグや地域研究機関との連携など、目的ごとのコンソーシアム(共同事業体)体制が見えてくる。ライセンス提供となればその仕組みづくりや運用も必要。コーディネータの存在もいっそう重要になってくるにちがいない。
Facebookは、
スマートフォンやタブレット、PCといったデバイスをジェスチャー操作する技術について、
デバイスからの距離情報の含まれる3次元(3D)ジェスチャーを
実現させる方法を考案した。
この技術を米国特許商標庁(USPTO)へ出願したところ、
米国時間1月3日に
「THREE-DIMENSIONAL GESTURES」(公開特許番号「US 9,535,596 B2」)
として登録された。
出願日は2012年7月25日、
公開日は2014年1月30日
(公開特許番号「US 2014/0028572 A1」)。

この特許は、
タッチパネル付き画面やトラックパッドなどの接触型ユーザーインターフェイス(UI)を採用するデバイスです。
ユーザーが指などでタッチした後に空中でジェスチャーして機能実行を指示する技術を説明したものです。
デバイスの種類は、
スマートフォンのように画面にタッチパネルが設けられているものだけでなく、
接触を検知するだけのセンサの設けられたものにも適用できるようです。

技術のポイントは、
タッチ後に指などとデバイスとの距離や、
指の動いた軌跡にもとづいて特定のジェスチャーを識別する部分です。
これによって3Dジェスチャー操作の識別が可能になり、
ジェスチャーのバリエーションが増えます。
操作内容に合った、直感的に覚えやすい指などの動きを
ジェスチャーとして採用しやすくなり、
ジェスチャー操作の実用性が向上するかもしれません。

3Dジェスチャーを識別するセンサとしては、
近接センサ、カメラ、タッチセンサなどが考えられます。
操作内容としては、音量や画面輝度など、さまざまな機能に適用できると思われます。

2017年1月25日の大学ジャーナルオンラインの記事によると、
産学連携(大学と起業の共同研究)が進んでいます。
共同研究費が、はじめて450億円を突破しました。
くわしくはこちらをごらんください。
産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、
国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」、
国際出願(日本語でされたものに限る)を行う場合には
「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。
この軽減措置は
平成26年4月から平成30年3月までに
特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象になります。
なお、
特許料の軽減に関しては、
平成26年4月から平成30年3月までに
特許の審査請求を行った案件が対象になります。
詳しくはこちら(特許庁のサイト)